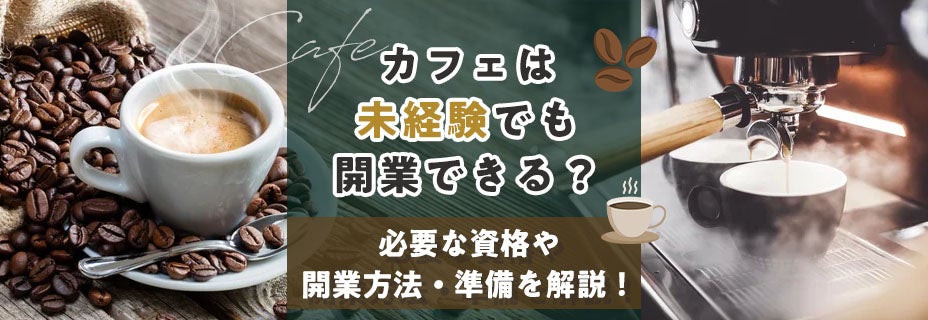
カフェは未経験でも開業できる?必要な資格や開業方法・準備を解説!
カフェ開業は、飲食業の実務経験がなくてもチャレンジできる人気のビジネスです。喫茶メニューを中心とした比較的シンプルな業態なので、初めての開業でも取り組みやすい点が魅力です。
ただし、運営を軌道に乗せるためには、店舗のコンセプトや必要な資格、運転資金など、事前の入念な準備が欠かせません。当記事では、カフェを未経験からでも開業するために知っておきたい基本情報や、具体的な開業方法、開業までの流れを分かりやすく解説します。
1.カフェは飲食業未経験でも開業できる?
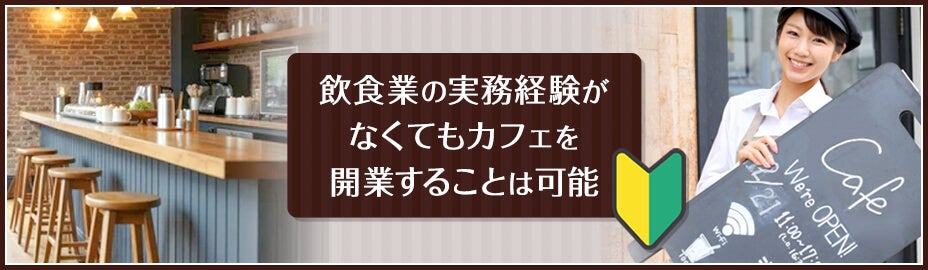
カフェは、飲食業の実務経験がなくても開業が可能です。飲食店の中でも、カフェは喫茶メニューが中心で、フードの種類も比較的少ないので、開業のハードルが低い業態と言えます。
ただし、コーヒーやフードにこだわった本格的なカフェを目指す場合は、抽出技術や盛り付け、経営知識などを習得しておくことが望ましいでしょう。運営形態や目指すコンセプトに応じた準備が、開業後の安定運営につながります。
1-1.カフェ開業に必要な資格や届けはある?

カフェを開業するにあたって経験は必要ないものの、法律に基づいた資格の取得や行政への届け出が必要です。ここでは、開業時に必要とされる主な5つの資格や届け出について、それぞれの概要を紹介します。
食品衛生責任者
食品を提供する店舗には、必ず1人以上の食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者になるには所定の講習を修了する必要があり、その後も定期的に講習会に出席しなければなりません。
防火管理者
収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者を選任しなければなりません。防火管理者は火災による被害を防ぐための講習を受け、火災予防や避難訓練の計画を担います。
飲食店営業許可申請
カフェを開店する前には、管轄の保健所へ飲食店営業許可の申請を行う必要があります。施設の構造や設備が基準を満たしているか、食品衛生法にもとづいて確認され、保健所による営業許可を受けることで開業できます。
菓子製造業許可申請
ケーキや焼き菓子などを店内で製造し販売する場合は、飲食店営業許可とは別に菓子製造業の許可が必要です。製造場所や設備などについて、要件が細かく定められています。
開業届
個人事業主としてカフェを運営する場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。開業日から原則1か月以内に提出が必要で、青色申告などの税制上の手続きにも関わる届出です。
2.カフェを開業する方法
カフェを開業する方法には、フランチャイズ加盟や独立開業のほか、実務経験や知識を身につけながら準備を進める方法など、さまざまな選択肢があります。自分の経験値や目指すカフェの方向性に応じて、最適な開業ルートを選びましょう。
ここでは、代表的な開業方法と、それぞれのメリットについて紹介します。
2-1.フランチャイズに加盟して開業する
フランチャイズに加盟して店舗名やブランド名を借り、カフェを開業する方法には、ブランド力や運営ノウハウを活用できるという大きなメリットがあります。業態に合った立地選定やメニュー構成、マーケティング方法などについてサポートを得られるので、経験が少ない人でも店舗を始めやすいでしょう。
また、開業後も本部のサポートが受けられる場合が多く、経営に不安がある人にとって安心感があります。ただし、初期投資額やロイヤリティの支払い、運営ルールの制限などが生じる可能性がある点には注意が必要です。
2-2.カフェで働きながら開業準備をする
開業前に実際のカフェで勤務経験を積んでから開業を目指すと、現場で必要なスキルや店舗運営の流れを肌で学べます。接客・調理・在庫管理など、実務を通じて得た知識は、独立後の運営に大きく役立つでしょう。さらに、自分に合った運営スタイルや方向性を見極めるヒントになったり、収入を得ながら開業資金を貯められたりする点も魅力です。
2-3.カフェスクールに通って開業する
カフェ開業を専門的に学べるスクールに通えば、短期間で効率的に知識と技術を習得できます。スクールではドリンクの抽出技術や調理、経営に関する基礎知識など、幅広く学べるカリキュラムが組まれているのが特徴です。卒業後に独立開業を支援する体制が整っている学校も多いので、現時点でカフェ運営の経験がない人にとって安心です。
費用や通学時間が必要になるものの、体系的な学習と実践的なスキルの両方を得られるので、独立に向けた基盤づくりに効果的です。
2-4.自力でカフェを開業する
自分の力のみでカフェを開業すると、店を開くときの自由度が高く、理想のカフェを実現しやすいでしょう。コンセプトやメニュー、インテリア、営業時間などをすべて自身で決められるため、個性を反映しやすくなります。また、独自の工夫や地域性を取り入れた運営が可能なので、うまくいけばリピーターの獲得につながることもあります。
一方で、開業資金の調達や物件選定、許認可取得などすべてを自身で行う必要があり、知識や準備が欠かせません。自力でカフェを開業する方法は、主体的に調べ、動ける人に適した方法です。
3.カフェを開業するまでの準備
理想の店舗を形にし、安定して経営を続けるためには、事前にさまざまな準備を整える必要があります。ここでは、開業前に行っておきたい主な準備項目を5つに分けて解説します。
3-1.お店のコンセプトを考える

開業準備の第一歩は、お店の明確なコンセプトを設定することです。ターゲットとする客層や提供するメニューの方向性、内装の雰囲気などを具体的に決めておくことで、店舗全体の統一感が生まれます。
たとえば「静かに読書ができるブックカフェ」や「自家焙煎コーヒーにこだわる専門店」などのコンセプトを決めると、他店との差別化がしやすくなります。また、事業計画や物件選び、メニュー開発の方針を決める際にも、コンセプトは重要な指針となります。
3-2.事業計画書を作る
カフェ開業に向けて資金調達や準備を進めるには、事業計画書の作成が欠かせません。事業計画書には、開業の目的や店舗コンセプト、ターゲット層、メニュー構成、立地条件、収支予測などを記載します。金融機関から融資を受ける際は、しっかり事業計画書を作りこむ必要があるので、数字やデータをもとに根拠を示すよう心がけましょう。
事業計画書は開業後も定期的に見直し、店舗の実情に応じた改善を加えることも大切です。
3-3.お店の運転資金を準備する
開業資金だけでなく、運転資金の確保も重要な準備項目です。運転資金とは、家賃や光熱費、仕入れ代、人件費など、開業後の店舗運営に必要な費用を指します。カフェの場合、黒字化までに数か月を要することもあるので、最低でも3~6か月分の運転資金を見込んでおくと安心です。
資金調達の手段としては、自己資金のほか、日本政策金融公庫や信用金庫からの融資、補助金・助成金の活用といった手段もあります。資金繰りが安定していると、開業後の経営リスクを減らせるでしょう。
3-4.お店の装飾やメニューを開発する
店舗の内装やメニュー構成は、来店動機やリピーター獲得に直結する重要な要素です。
お店の装飾に関しては、ターゲットやコンセプトに合った雰囲気づくりが求められます。ナチュラルな木目調や北欧風、インダストリアル風など、デザインを統一すると印象が良くなります。
メニューについては、提供のしやすさや利益率、季節ごとの変化も考慮しながら選定します。看板商品を用意することで店の個性を打ち出せるので、開業前に試作や試食を重ね、じっくり検討しましょう。
3-5.必要なものを準備する
カフェ開業には、多くの備品や設備が必要となります。主なものとしては、コーヒーマシンやグラインダー、冷蔵庫、調理器具、食器類、レジシステム、椅子・テーブルなどが挙げられます。また、看板やメニュー表、ユニフォームなども忘れてはなりません。
備品を準備する際は、購入するものとレンタルで済ませられるものを分類すると初期費用を抑えられます。また、仕入れ先の選定や契約手続きは事前に済ませ、スムーズに開店準備を始められるようにしましょう。
まとめ
カフェの開業は実務経験がない人でも可能で、フランチャイズへの加盟やスクールの受講、自力開業など開業までにはさまざまな手段があります。理想のカフェを実現するために明確なコンセプトを設け、必要な資格や許認可の取得、事業計画書の作成、資金の確保など、必要な準備を進めましょう。
カフェのメニューを考える際は、仕入れについても検討する必要があります。ミクリードでは手間のかからない食材を多数ご用意しておりますので、カフェメニューや仕入れでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
酒類の取扱いについて
20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されており、20歳未満の方に対して販売はいたしません。
みりん・料理酒等の取扱いについて
掲載商品名頭に「L」のつく商品につきましては、弊社の酒類販売媒介業免許に基づき、弊社が国分グループ本社株式会社の販売する酒類商品の注文を取次ぎます。
酒類販売
管理者標識
販売場の名称
及び所在地
酒類販売
管理者の氏名
酒類販売管理
研修受講 年月日
次回研修の
受講期限
研修実施
団体名
株式会社ミクリード
東京都新宿区西新宿2-3-1
守屋 賢邦
(モリヤマサクニ)
令和7年 6月18日
令和10年 6月17日
一般社団法人日本
ボランタリーチェーン協会
国分グループ本社株式会社
東京都中央区日本橋1-1-1
西川 貴志
(ニシカワタカシ)
令和6年 5月16日
令和9年 5月15日
一般社団法人日本
ボランタリーチェーン協会


















